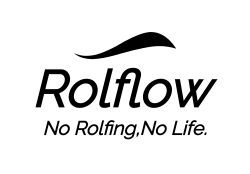私のセッションでは、セッションを始める前に事細かな説明はあまりしない。またセッション後に宿題や課題を出すこともほとんどない。なぜなら自分があまり好きでないので。
実はセッションで基本的なことはレシピに沿って同じことを行っている。(ことが多いぐらいかな。)
しかし、受け手によって感じることやそこから起きる結果は全く異なる。ホントに十人十色なのだ。
なので、こういうことを目的で行うためにどういったことをするといったある意味理論的なものが邪魔になったり無意味になることがある。
これは理論が必要ないということではない。あくまでその理論をその時必要として感じた受け手の感受性が大切と感じている。
全てを理論的に構築して導くスタイルもあり、それはそれで憧れる。
知識と情報を駆使し、さらにそれを叶える技術が伴って、その結果ほらスゴイだろと。
でも、私のスタイルはどちらかというと、自分もクライアントもいわゆる理論がまだたたないところに向き合った時の偶発的な何かがもたらす方に期待して一緒にスゴイねと味わうニュアンスだ。
一方的に教えるのでなく一緒に感じたことを互いに表現して交わしていく。
これがセッションたる所以だ。
セッションに参加できる余白や余地があるのは、プラクティショナーとクライアント双方にとって、対等な関係性で心地よいものだ。
余白
アナトミートレインのアシスタントしてきました。その1

日本のトレーニング最先端の情報を提供していると言っても過言ではないkinetikos(キネティコス)を主催するロルファーの大先輩の谷佳織さん、そして自身がトレーニングの見本となる的確な動きと指導に定評のあるロルファー大室泰三さんのお招きを受けて、トム・マイヤーズ(Thomas Myers)を迎えてのアナトミートレイン・ストラクチャー&ファンクション(Anatomy Trains Structure & Function)の2日間実技クラスに実技指導アシスタントとして行ってきました。
実は私がロルフィング®をロルファー™を志したのは、著書Anatomy Trainsの情報に驚き、この進んだ情報を得るにはこのコミュニティに飛び込むしかないと思ったのがキッカケ。
そしてロルファーになってすぐにトム・マイヤーズ初来日の際に生徒としてワークショップに参加したのが17年前。歳月を経ての再会はアシスタントという立場で協力できるのは思いもよらずウレシイ限り。
日本各地だけでなく、カナダ、シンガポール、オーストラリアからも集まった皆さんが言語の壁を超えて、触れることで繋がる素晴らしい熱量、素晴らしい空間。まだ来週も続きますので、さらに期待が高まります。
月刊トレーニングジャーナル2018年1月号にRolflow上大岡でのロルフィング個人セッションの様子が掲載されました

月刊トレーニングジャーナル2018年1月号にRolflowロルフロー上大岡にてロルファー松永直之(まつながなおゆき)のロルフィングセッションの様子をレポートして頂いた記事が掲載されました。
ロルフィングに関心を寄せて頂いた西澤隆(にしざわたかし)氏をはじめ、「ロルフィングが少しでも世の中に広まってくれるなら、喜んで!」とセッション中の写真撮影を含めた慣れない取材を快く引き受けてくださったTさんのご協力に、心より感謝申し上げます。
※下記の掲載記事は、PCの場合はそのまま埋め込みPDFの画面で表示されます。スマートフォン・タブレットの場合は埋め込みPDF画面は表示されず、お手元の端末にダウンロードされた後にご覧頂けます。
カルチャーセンターさいか屋横須賀店でワークショップ。
Facebookで知って詳細を見にカルチャーセンターさいか屋横須賀店様のホームページを見たけれど、検索してもでてこないよ!とお知らせを受けたので、改めてご案内します。
※定期開催扱いとなる前の段階のため検索できず、トピックスとしての特設ページ扱いです。どんな人がやるのか?はたまたロルフィング®の文言もホームページ上には記載されず、添付PDFにのみ記載されているのでその掲載画像を引用します。


講座名は「-感覚を磨いて健やかに- 身体感覚アップ 」。
以前に比べて何だかカラダの調子がいまひとつ、自分のからだなのになぜかうまく動かせない・・と健康やカラダのことでお悩みのことはありませんか?改善するための方法があまた飛び交う今日。ただどんな方法であってもそれを知ったとして自分自身で実現できるのは別の話しとなってしまうことが多いようです。そこで実現できる自分作りの第一歩として身体感覚をアップさせることが鍵になります。
「身体感覚をアップ、感覚を磨く」と言葉にすると、それに秀でた達人や繊細な方じゃなきゃダメじゃないかしら・・難しそうと思われるかもしれませんが、むしろその逆。知らないからこそ、思い込みがないからこそ、ちょっとしたヒントでスッと新たな感覚を得やすいです。
実際に自分のからだに触れ、感じ、動く、と五感をさらに第六感までをもフル活用して今まで意識したことのないところを目覚めさせ、変化していく身体感覚を一緒に体験し味わう場にできればと思っています。
ちなみに今回は紙面と商標の関係でロルフィングの文字を講座名に反映できませんでしたが、ロルフィングの考え方を軸に、からだの仕組み、運動制御や身体認知の分野にスポーツや介護現場での臨床的知見や東洋医学的観点を織り込みつつ、ボディワークの世界を一緒に感じましょう。
カルチャーセンター横須賀さいか屋様サイトの掲載ページはこちら⇒
身体の仕組みに触れて、普段とは違う意識や感じ方で動くと変化していく体の感覚の面白さを一緒に体験します。
第1・3(水)13:00~14:30
◆受講料 ¥5500【無料体験会】
10/4、10/18(水)13:00~14:00<受講される場合>
事務手数料*受講料→3ヶ月分前納制です
*別途運営維持費¥250/月を頂きます
どの講座も事前のご予約が必要です。
原則キャンセルは出来ませんのでご了承ください。
お電話お待ちしております。カルチャーセンターさいか屋横須賀 046-828-5911
Body Image(ボディイメージ:身体イメージ)とBody Schema(ボディスキーマ:身体図式)
聞きなれない言葉:ボディスキーマ
ロルフィングにおいて明確な効果が表れる大きな要因は、Body Schema ボディスキーマ:身体図式にアクセスすることによる。身体図式の文字だけを眺めると、もっと普通になじみあるBody Image ボディイメージ:身体イメージと何か違いがあるのかしら?と思うだろう。実は大きく異なる。
ボディイメージは、後天的つまり体験や学習から獲得した情報により作り上げられる。
これに対してボディスキーマは先天的に形や大きさ、また質感など最初からそこにあるものをさす。またさらにはこのあるものあるものとして感じる能力までを含んでいるといっていいだろう。
急に振り返ると気持ち悪くなる
頭の中で慣性の法則
「急に振り返ると気持ち悪くなるんです。」と、ご相談頂いた。はて?どうしたものか。この時のヒントになったのが、いつも傍らでしっぽフリフリしてご機嫌ワンちゃん・トイプードルのMクン。
その方の動きを再現してもらうと、振り返る=頭部を左右にひねる動作において、背骨全体を介した連続性の動作がないということ。私はいつも自分でクライアントさんの動きをコピーして感じ取るのだが、今回の場合ちょうど首の骨の頸骨の7番目と背骨の胸骨1番目あたりで連続性が途切れる。
※物は試し、首の付け根のあたりをちょっと固めるようにし、首から上だけで勢いよく振り返り、回転を急激に止めてみてください。やり過ぎ注意。
振り返り動作が急激にストップした瞬間、頭や体の外側は止まるけど頭の中の脳がモロに揺れてしまう気持ち悪さを感じる。
この現象を分析してみると、頭部がねじれ、そのねじった力が背骨のひとつひとつをうねりのパワーとして下方に伝達される。本来この下方へねじれの力が伝達する過程で力が減衰するため、見かけ上急に振り返っても、脳内が揺らされるまでの勢いがうまく消える。しかし、頸骨と胸骨の境界付近で背骨を介した下方への伝達が行われない場合は、この回転の勢いが減衰せず、脳内が回旋し、また伝達の境目で跳ね返されたねじれパワーがさらに脳内を逆方向へゆらすといった具合になるのだ。
これを解決するための作戦。足裏が適切に着くようにベッドサイドに座り、首をゆっくり左右に回してもらう。私はその首の動きに合わせて、首の骨からひとつひとつ背骨が左右にねじれる動きを誘導し、これを背骨の再下端である尾骨までつなげていく。そうそう先のワンちゃん話は何だったんだということが、ここに結び付いてくる。
振り返るという動作は首から上だけを動かす動きにあらず、背骨全体がなびく動作。この本来あるべき連続性のある動きを取り戻す。このムーブメントの後、急に振り返る動作をしてもらったところ、頭の中が揺らされるようなことがなく、気持ち悪くならないと不思議そうに一言。
しっぽフリフリで気づかせてくれたトイプードルのワンちゃんMクンに感謝。